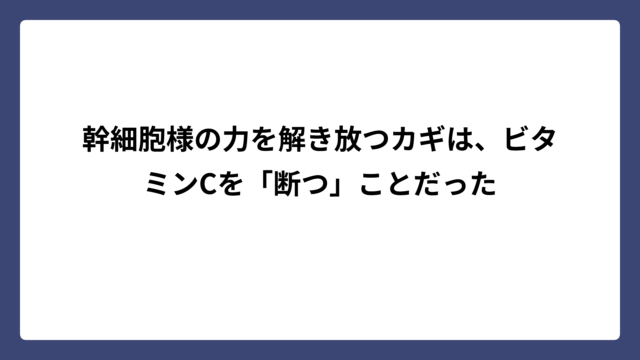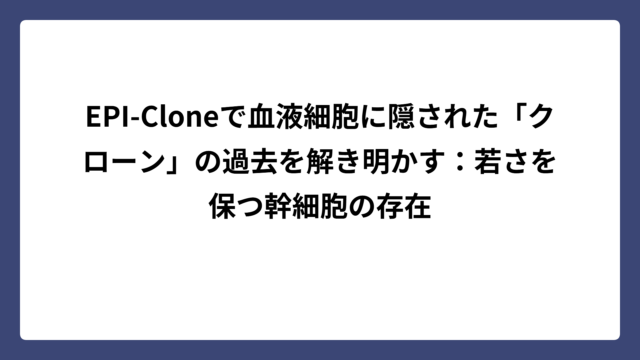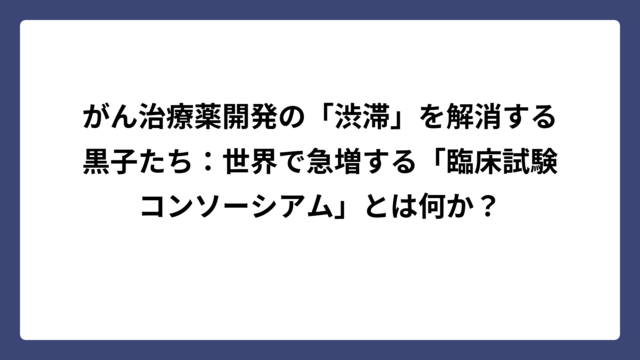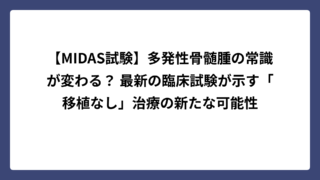「がん」という診断は、多くの人にとって人生を揺るがす出来事です。闘病生活への不安に加え、将来子どもを持つことを望む若い世代の患者さんにとっては、「妊よう性が失われるかもしれない」という、もう一つの大きな精神的負担がのしかかります。しかし、がん治療の進歩によって多くの患者さんが長い人生を歩めるようになったからこそ、その先の人生の質、特に家族を持つという希望を守ることが、これまで以上に重要な課題となってきています。
キーポイント
- 卵巣組織凍結は、もはや「実験的」ではなく「確立された選択肢」へ
- 治療後の妊よう性温存も可能に。ただし、注意点も
- 小児・思春期世代にも、男女別の温存法が明確に示された
- 卵巣機能の「保護」は、温存の「代替」にはならないという理解が重要
- すべての技術の土台となる、最も重要な第一歩は「話し合うこと」
1. 卵巣組織凍結は、もはや「実験的」ではない「確立された選択肢」に
標準的な妊よう性温存法である卵子や胚の凍結は、ホルモン剤で卵巣を刺激し、採卵するまでに数週間の時間が必要です。一部の患者さんにとっては、がん治療をすぐに開始する必要があり時間的な余裕がなかったり、ホルモンががんの進行に影響するリスクがあったりするため、この方法が選択できませんでした。
今回のガイドライン改訂では、卵巣組織凍結保存(Ovarian Tissue Cryopreservation: OTC)が、正式に「確立された妊よう性温存法」として位置づけらました(勧告4.10)。これは、手術で卵巣の一部を摘出して凍結保存する技術で、ホルモン刺激が不要なため、がん治療の開始を遅らせる必要がありません。これまで選択肢が限られていた、あるいは閉ざされていた患者さんたち(特に思春期前の女児)にとっては唯一の確立された選択肢となります。
ガイドラインに示されたデータによると、卵巣組織凍結による出産率(Live Birth Rate)は19%~32%に達しており(Table 2)、とても希望の持てる数字です。さらに、将来の妊娠だけでなく、移植した組織からホルモンが分泌されることで、卵巣機能そのものを回復させる効果も期待されています。
2. 「もう手遅れかも」は間違い? がん治療後の妊よう性温存も可能に
卵巣組織凍結のような重要な選択肢が確立された一方で、「治療が始まる前に温存の機会を逃してしまったら、もう手遅れだ」と考える患者さんは少なくありませんでした。しかし、今回のガイドラインは、その点においても新たな希望を示しており、「治療後の妊よう性温存」という選択肢を明確に推奨しました(勧告4.3)。治療前に妊よう性温存の機会がなかったり、保存した卵子や胚の数が十分でないと感じたりする患者さんでも、治療後に卵巣機能が回復すれば、改めて卵子や胚を凍結保存することが可能であると明記されたのです。
ただし、この新しい選択肢には重要な注意点があります。ガイドラインは、化学療法終了直後は質の良い卵子が採れない可能性や、治療後間もなく採取された卵子の生殖能力や、それによって生まれる子どもの健康への影響についてはまだ十分に分かっていないと指摘しています(勧告4.3の注釈)。卵巣機能がどの程度回復するかに依存するため、希望とともに慎重なカウンセリングが不可欠です。それでも、この選択肢が公式に示されたことは、がんサバイバーが長期的な視点で自身の人生を再設計する上で、非常に大きな一歩と言えるでしょう。
3. 子どもたちにも選択肢を。小児・思春期世代の妊よう性温存
小児がんの治療成績は飛躍的に向上し、多くの子供たちががんを乗り越えて長い人生を歩む時代になりました。医療の役割は、単に命を救うだけでなく、その後の人生の質(Quality of Life)をいかに豊かにするかという点に移りつつあります。その中でも、将来家族を持つという選択肢を守ることは極めて重要です。
ASCOのガイドラインでは、小児・思春期世代の患者さんに対する妊よう性温存の選択肢が、男女別にこれまで以上に明確に整理されました。
- 思春期前の女児: 唯一の確立された選択肢として「卵巣組織凍結保存(OTC)」が推奨されています(勧告5.1)。これは、まだ採卵ができない低年齢の女児にとって、将来の可能性を残すための唯一かつ有効な方法となります。
- 思春期前の男児: 唯一の選択肢として「精巣組織凍結保存(TTC)」が挙げられていますが、こちらは現時点ではまだ「臨床試験段階」と位置づけられています(勧告3.4)。将来の技術確立に期待が寄せられるものの、まだ研究的なアプローチであることが明確に区別されています。
4. 卵巣機能の「保護」は温存の「代替」にはならない
妊よう性温存について考えるとき、様々な選択肢の役割を正確に理解することが不可欠です。特に、広く知られている治療法がどのような目的で使われ、その限界はどこにあるのかを知ることは、最適な選択をするために重要です。
GnRHa(ゴナドトロピン放出ホルモンアゴニスト)を用いた「卵巣抑制療法」は、化学療法中に卵巣を一時的な休眠状態にすることで、抗がん剤によるダメージを「隠れて」やり過ごさせようという治療法です。しかし、ASCOガイドラインはこの治療法の位置づけについて、これまでの温存とは明確に区別しています。つまり、化学療法から守るために卵巣機能を「抑制」する戦略と、将来のために卵子や組織を物理的に体外へ取り出して「温存」する戦略は、根本的に異なり、確実性も大きく違うのです。
ガイドラインは、卵巣抑制療法は、卵子や胚、卵巣組織の凍結といった確立された妊よう性温存法の代替とはならない乳がん患者に対する補助的な治療として、あるいは緊急で化学療法を開始する必要がある場合の選択肢として限定的に推奨されうる、としています(勧告4.8, 4.9)。「温存」法の代替とはならない、という専門家の一致した見解が示されています。
5. 最も重要な第一歩は「話し合う」こと
今回のガイドラインが最も強く強調しているのは、患者さんと医療者のコミュニケーションです。ガイドラインでは、がん治療が妊よう性に与えるリスクについて、治療を開始するできるだけ早い段階で話し合うことを、すべての医療者に強く推奨しています(勧告1.1)。この対話は、ありません。
ガイドラインは、この話し合いは特定の患者さんだけのものだけではなく、すべての患者にとって不可欠であると説明しています。すなわち、患者の妊よう性リスクの程度、現在の家族構成、がんの予後、性的指向や性自認、宗教的信条、経済状況や保険の有無、医療へのアクセスなど、いかなる背景にも関わらず、「すべての患者」と話し合うことが極めて重要です(勧告1.3, 1.4の注釈)。
この「話し合う」という行為そのものに、大きな価値があると科学的にも示されています。たとえ最終的に妊よう性温存という選択をしなかったとしても、事前に十分な情報提供を受け、自身の将来について考える機会を持つことは、患者さんの精神的苦痛を和らげ、将来の後悔を減らし、QOL(生活の質)の向上につながることが研究で明らかになっています。最新の技術を最大限に活かすためには、まず患者さん一人ひとりの希望や価値観に寄り添う、丁寧な対話から始めなければならないのです。
まとめ
がん治療における妊よう性温存の世界は、技術の進歩と、患者さん一人ひとりの人生に寄り添う「患者中心のケア」という考え方の成熟によって、大きく変化しています。卵巣組織凍結が標準治療となり、治療後の温存も可能になるなど、選択肢は着実に広がり、より多くの患者さんに希望をもたらしています。
しかし、最も重要なのは、これらの選択肢が存在することを患者さん自身が知り、医療者と対話をしっかりと行い、自分らしい未来を選択する機会を得ることなのです。