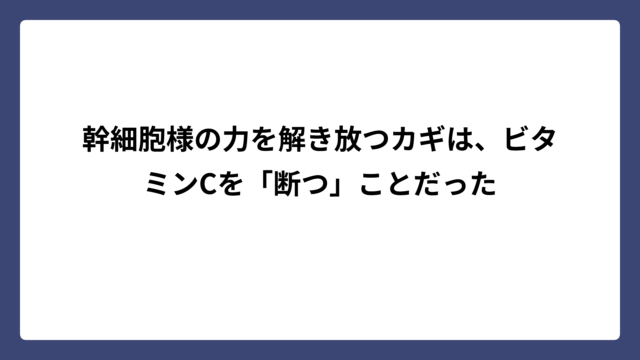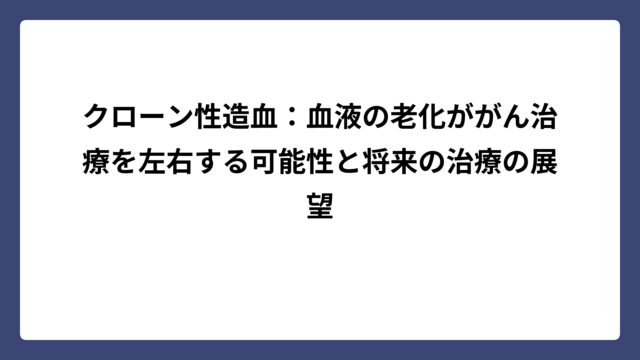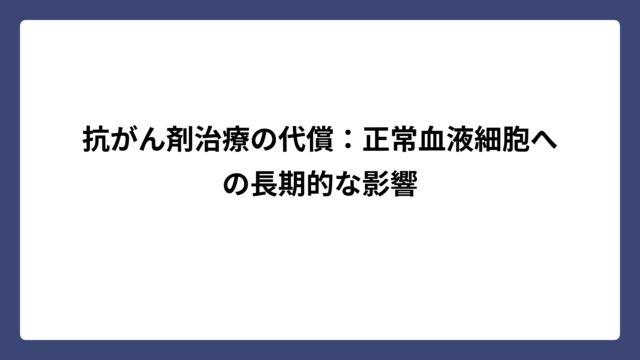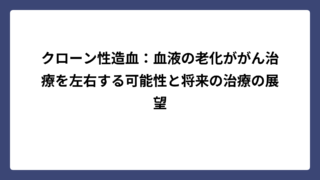現代医療において、CTスキャンやX線検査などの画像診断は、病気の早期発見や治療方針の決定に欠かせない役割を果たしています。しかし、その利便性の裏側には、電離放射線への曝露というリスクが常に存在します。特に身体が成長過程にあり、放射線への感受性が高い子どもたちにとって、この「見えない曝露」の影響を解明することは、小児科医療において非常に重要です。
2025年にNEJMに掲載された「小児・思春期がん画像診断リスク(RIC)研究」は、370万人以上を対象とした過去最大級のものです。この研究では「小児血液がんの約10.1%が画像診断に起因する」という推計は、単なる統計データではなく、現代医療に対する「公衆衛生上の問題」となることを示唆しています。過剰な検査を抑制し、真に「必要な検査」を見極めることが、親と医療提供者にとっての重要な課題となるでしょう。
キーポイント
- 明確な用量反応関係: 骨髄への累積放射線量が増えるにつれて、血液がんのリスクは有意に上昇します(100 mGyあたりの過剰相対リスク 2.54)。
- 「安全な閾値」の不在: 1 mGy未満(>0 to <1 mGy)という極めて低線量の曝露であっても、非曝露群と比較して1.16倍の統計的に有意なリスク上昇が認められました。
- 高い寄与率(10.1%): 本研究コホートにおける小児血液がんの10件に1件は、医療被ばくが原因であると推定されました。特に頭部CTのような高線量検査が、この集団リスクを押し上げる主要因となっています。
- 特定のサブタイプにおける顕著なリスク: 累積30 mGyの曝露において、組織球・樹状細胞がんのリスクは7.00倍、骨髄異形成症候群(MDS)のリスクは4.06倍にまで跳ね上がります。
RICコホートの詳細
「RICコホート」は、米国とカナダの医療システムを利用した3,724,623人の子どもを対象としたレトロスペクティブ・コホート研究です。
背景と目的
米国は一人あたりの画像診断数が世界で最も多い国の一つですが、北米における包括的なリスク評価はこれまで不足していました。本研究は、CTだけでなく、X線、血管造影、核医学検査を含む全画像診断を網羅し、骨髄への累積線量を精密に定量化しました。
結果:リスクの動態とがんの種別
平均10.1年の追跡期間中に2,961件の血液がんが診断されました。
- 特定の疾患への強い影響: 血液がん全体のリスクだけでなく、累積30 mGy曝露時における組織球・樹状細胞がん(RR 7.00)や、骨髄異形成症候群(RR 4.06)への高い影響が示されました。
- 年齢と時期のパラドックス: 曝露時の年齢が5歳以上の群の方が、乳幼児期よりもリスクとの関連が強く出る傾向が確認されました。また、リスクは曝露から1〜4年以内の初期に最も高く、時間経過とともに弱まる傾向を示しています。
- ダウン症などの遺伝的要因を制御し、さらに「がんの初期症状のために検査が行われた」という逆因果関係を排除するため、6ヶ月および24ヶ月のラグの期間を設けても、リスク上昇の結果は揺るぎませんでした。
累積線量とがんリスクの相関
本研究は、放射線曝露量と血液がん発症の間に、統計的に有意な関連があることを明らかにしました(P<0.001)。累積放射線量が100 mGy増加するごとの過剰相対リスク(ERR)は2.54(95%信頼区間 1.70–3.51)という数値が算出されています。
重要な点は、これまで無視できると考えられてきた低線量域でのリスクです。
- >0〜1 mGy未満: 相対リスク 1.16
- 1〜5 mGy未満: 相対リスク 1.41
- 30 mGy(一般的なCT数回分): 相対リスク 1.76
累積線量が100 mGyを超えると、リスクは非曝露群の5.64倍に達します。この「用量反応関係」は、画像診断が血液がんの重要なリスク因子であることを示しています。
本文では、骨髄への累積放射線量は、すべての血液がんのリスク増加と有意に関連していた(100 mGyあたりの過剰相対リスク 2.54 [95%信頼区間 1.70–3.51; P<0.001])、と記載されています。
CTスキャン vs. X線:リスクの質的違い
とはいえ、すべての画像検査を同一視すべきではありません。リスクの大部分は、一部の高線量検査に集中しています。
- 頭部CT: 1回あたりの骨髄線量は平均13.7 mGy。この検査を受けた群では、発症した血液がんの25.9%が被ばくに起因すると推定されます。
- 胸部X線: 1回あたりわずか0.01 mGy。寄与率は0.03%に過ぎません。
頭部CTは頻度が高く、かつ1回あたりの線量も大きいため、人口寄与危険度(PAR)の大部分を占めています。つまり、CTの適正化こそが、子どもの血液がんの予防において最も介入の価値がある部分と考えられます。
臨床現場への示唆
本研究では、画像診断を否定せず、その「質的最適化」を求めています。
- 低価値な検査の削減: 診断に直結しない「念のため」の検査を減らすことは、最も効果的な予防策です。10.1%という寄与率は、臨床医が「今は検査をしない」という判断を下す際の科学的根拠となりえます。
- 代替手段への転換: 放射線を使用しない超音波やMRIへの代替、あるいは小児専用の低線量プロトコルの採用を標準化すべきです。
もちろん、「必要な検査を控えるリスク」を無視してはいけません。重症外傷などの緊急事態において、画像診断は命を救うために重要です。重要なのは、「将来のリスク(がん)」と「現在の利益(診断)」のバランスを考慮することです。
さいごに
医療画像診断の恩恵は非常に大きなものです。しかし、その恩恵には「累積的な代償」が伴うことが示されました。血液がんの10%が予防可能かもしれないという点は、画像検査を行うかどうかを考える重要なポイントとなります。
「この検査によって治療方針はどう変わりますか? 放射線を使わない代替案や、より低い線量で行う方法はありますか?」
その一つの問いかけが、医療の恩恵を最大限に引き出しつつ、子どもの未来を守るための確かな一歩となるのです。