Warning : Undefined array key "url" in /home/c9357971/public_html/med.science.pink-nez.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math/includes/modules/schema/snippets/class-author.php on line 41
Multiple Myeloma
【CARTITUDE-4】生存期間だけでなく「生活の質」をも劇的に改善する多発性骨髄腫治療:Cilta-cel
サイエンスと治療薬の世界
Mina, Roberto et al. “Patient-reported outcomes following ciltacabtag …
Myeloid
ありふれた糖尿病治療薬メトホルミンが血液がんの前駆状態を抑制する可能性
サイエンスと治療薬の世界
Hosseini, Mohsen et al. “Metformin reduces the competitive advantage …
Multiple Myeloma
【CEPHEUS試験】D-VRdが多発性骨髄腫の新たな標準治療へ:試験が明らかにした4剤併用療法の力
サイエンスと治療薬の世界
Usmani, Saad Z et al. “Daratumumab plus bortezomib, lenalidomide and …
Genomics
なぜ男性は短命なのか? Y染色体の消失が引き起こす影響とは
サイエンスと治療薬の世界
Bruhn-Olszewska, Bozena et al. “The effects of loss of Y chromosome o …
Multiple Myeloma
がんの「前段階」は、すでに「がん」だった?ゲノム解析による多発性骨髄腫の個別化医療の未来
サイエンスと治療薬の世界
Maura, Francesco et al. “Genomics Define Malignant Transformation in …
Multiple Myeloma
【MajesTEC-3】Teclistamab-Daratumumab併用療法が多発性骨髄腫治療の常識を覆す成績を示す
サイエンスと治療薬の世界
Costa, Luciano J et al. “Teclistamab plus Daratumumab in Relapsed or …
Multiple Myeloma
多発性骨髄腫のCAR-T細胞の持続性を劇的に高めるCDKN1Bの無効化の発見
サイエンスと治療薬の世界
Knudsen, Nelson H et al. “In vivo CRISPR screens identify modifiers o …
Multiple Myeloma
【AQUILA試験】高リスクくすぶり型骨髄腫への新戦略:早期治療の重要性
サイエンスと治療薬の世界
Dimopoulos, Meletios A et al. “Daratumumab or Active Monitoring for H …
Multiple Myeloma
多発性骨髄腫治療の最前線:EHAとEMNのガイドライン2025
サイエンスと治療薬の世界
Dimopoulos, Meletios A et al. “EHA-EMN Evidence-Based Guidelines for …
Endocrinology
人気の痩せ薬GLP-1作動薬、がんリスクを低下させる可能性が明らかに? — ただし注意点も
サイエンスと治療薬の世界
Dai, Hao et al. “GLP-1 Receptor Agonists and Cancer Risk in Adults Wi …
Multiple Myeloma
なぜ難治性がん「骨髄外多発性骨髄腫(EMM)」は免疫療法に抵抗するのか?免疫細胞の実態にせまる
サイエンスと治療薬の世界
Anilkumar Sithara, Anjana et al. “Composition and functional state of …
Multiple Myeloma
【MRD2STOP】多発性骨髄腫、治療はいつまで?最新研究が示す「やめどき」の新たな指標
サイエンスと治療薬の世界
Derman, Benjamin A et al. “Discontinuation of maintenance therapy in …
Multiple Myeloma
多発性骨髄腫の維持療法、中止すべきか? 治療が招く「二次がん」のリスクを最新研究が解き明かす
サイエンスと治療薬の世界
Cooperrider, Jennifer H et al. “Evolution of clonal hematopoiesis on …
Hematology
がん治療薬開発の「渋滞」を解消する:世界で急増する「臨床試験コンソーシアム」とは?
サイエンスと治療薬の世界
Liu, Jia et al. “Accelerating the Future of Oncology Drug Development …
Multiple Myeloma
治療薬が「がん」になる?革命的ながん治療法CAR-T細胞療法に潜む稀なリスクとは
サイエンスと治療薬の世界
Braun, Till et al. “Multiomic profiling of T cell lymphoma after ther …
CLL/SLL
奇跡の癌治療:たった1つの細胞が末期の白血病を完治させた驚きのメカニズム
サイエンスと治療薬の世界
Fraietta, Joseph A et al. “Disruption of TET2 promotes the therapeuti …
Multiple Myeloma
多発性骨髄腫治療の新たな一手か?Tec/Talの2剤併用療法が示す「驚異的な有効性」と「課題」
サイエンスと治療薬の世界
Cohen, Yael C et al. “Talquetamab plus Teclistamab in Relapsed or Ref …
AML/MDS
難治性白血病の新たな弱点を発見:最先端研究が解き明かす薬剤耐性の克服戦略
サイエンスと治療薬の世界
Wegmann, Rebekka et al. “Single-cell landscape of innate and acquired …
AML/MDS
高齢者の急性骨髄性白血病(AML)治療が変わる:米国血液学会(ASH)2025年新ガイドライン
サイエンスと治療薬の世界
Sekeres, Mikkael A et al. “American Society of Hematology 2025 guidel …
Leukamia
栄養ドリンクに含まれる「タウリン」が、白血病を悪化させる燃料だった?
サイエンスと治療薬の世界
Sharma, Sonali et al. “Taurine from tumour niche drives glycolysis to …
Multiple Myeloma
【MonumenTAL-1】多発性骨髄腫治療の新たな希望:GPRC5Dを標的とする新薬タルケタマブtalquetamab が示す卓越した効果
サイエンスと治療薬の世界
Chari, Ajai et al. “Safety and activity of talquetamab in patients wi …
Multiple Myeloma
多発性骨髄腫治療の「順番」が生存を左右する:欧州骨髄腫ネットワークEMNが示す4つの新常識
サイエンスと治療薬の世界
van de Donk, Niels W C J et al. “Sequencing BCMA- and GPRC5D-targetin …
Thrombosis/Hemostasis
小児ITP治療に新時代到来か?標準治療を上回るエルトロンボパグの有効性を示した最新臨床試験【PINES試験】
サイエンスと治療薬の世界
Shimano, Kristin A et al. “Eltrombopag for Newly Diagnosed Pediatric …
Multiple Myeloma
多発性骨髄腫の「ハイリスク」を再定義する:最新の国際コンセンサスIMWG2025が示す4つの重要な変更点
サイエンスと治療薬の世界
Avet-Loiseau, Hervé et al. “International Myeloma Society/Internation …
AML/MDS
なぜ有望な抗がん剤開発は失敗するのか? 高リスク骨髄異形成症候群(HR-MDS)の臨床試験から学ぶ5つの教訓
サイエンスと治療薬の世界
Stahl, Maximilian F, and Amer M Zeidan. “The conundrum of drug develo …
ALL
【小児白血病治療の常識を覆す?】アスパラギナーゼによる膵炎後の「再挑戦」が命を救う
サイエンスと治療薬の世界
小児急性リンパ性白血病(ALL)の治療に不可欠な薬剤「アスパラギナーゼ」。この薬は白血病細胞を効果的に攻撃する一方で、時に重篤な副作用であ …
Cardiovascular
【CTX310】コレステロール治療に革命?CRISPR遺伝子編集の「1回で終わる」新治療
サイエンスと治療薬の世界
高いコレステロールや中性脂肪の値をコントロールするため、毎日薬を飲み続ける——これは多くの人にとって、生涯にわたる身近な課題です。しかし、 …
Multiple Myeloma
【CARTITUDE-4】多発性骨髄腫治療の未来を変える?CAR-T療法「シルタセル:Cilta-cel」が標準治療を74%上回った衝撃の臨床試験結果
サイエンスと治療薬の世界
San-Miguel, Jesús et al. “Cilta-cel or Standard Care in Lenalidomide- …
AML/MDS
【HARMONY Alliance試験】MDS del(5q)患者におけるLenalidomide治療中止後の輸血依存のない状態の維持
サイエンスと治療薬の世界
引用
Crisà, E., Mora, E., Germing, U., et al. Transfusion independen …
Multiple Myeloma
多発性骨髄腫のレナリドミド維持療法を3年間のMRD陰性状態後に中止してもMRD陰性は維持される
サイエンスと治療薬の世界
第21回International Myeloma Society Annual Meetingで、多発性骨髄腫におけるlenalidom …
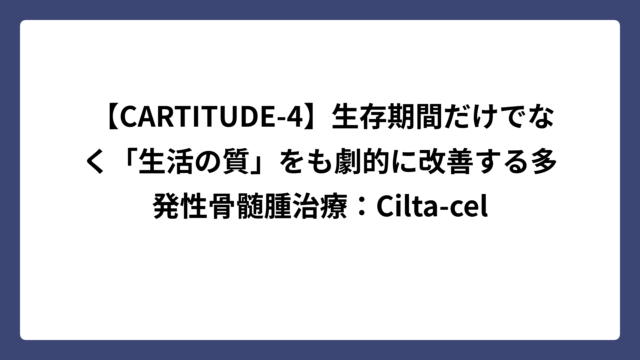 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
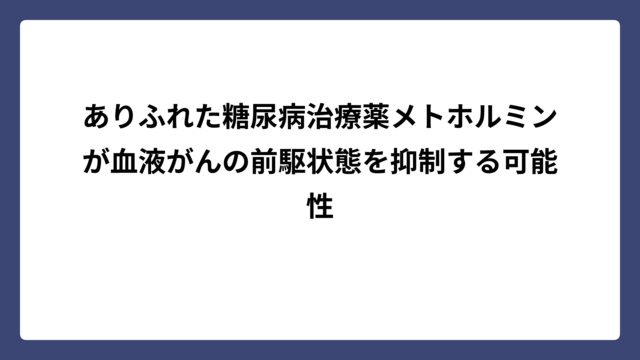 Myeloid
Myeloid
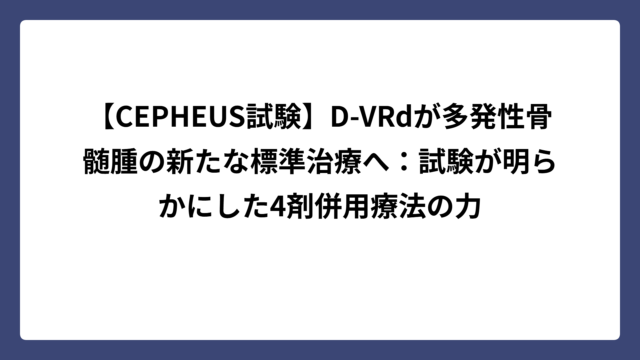 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
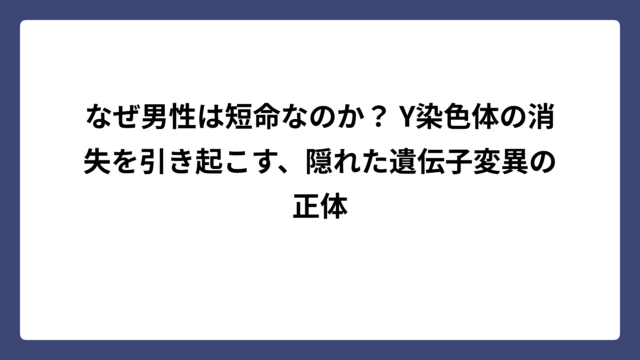 Genomics
Genomics
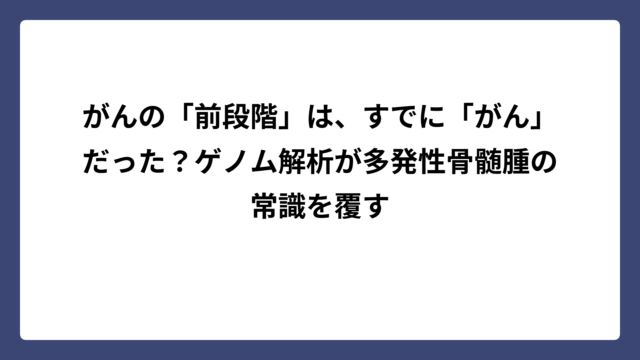 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
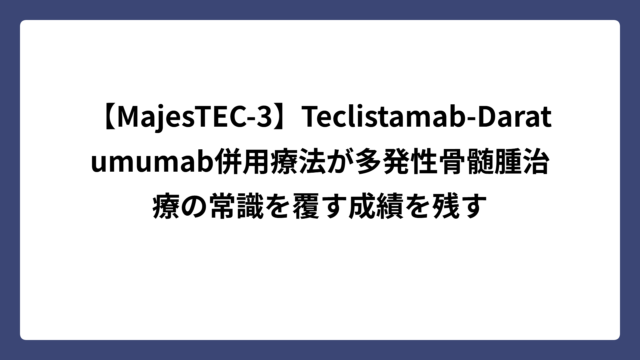 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
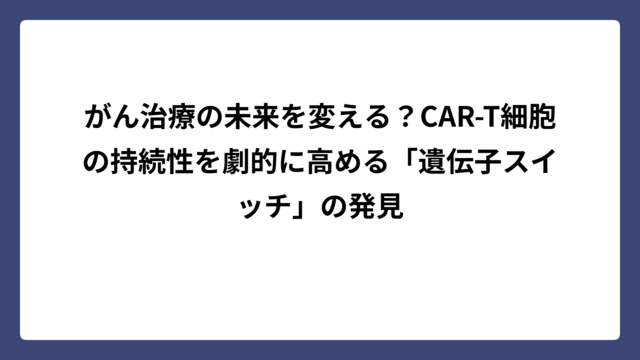 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
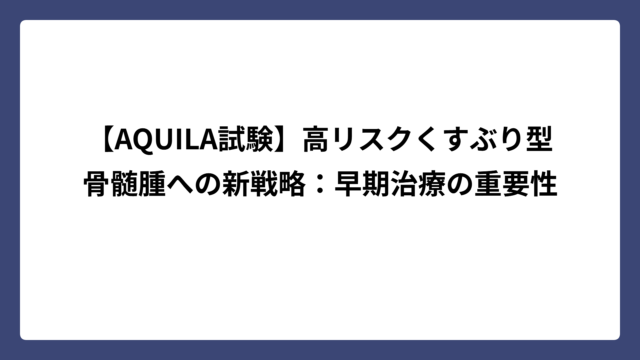 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
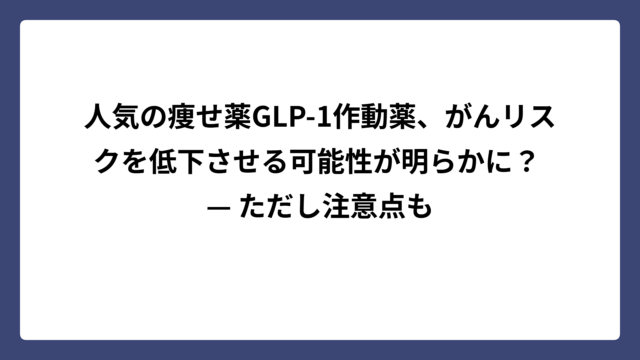 Endocrinology
Endocrinology
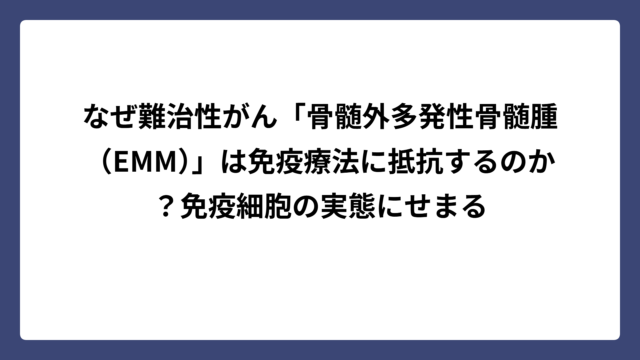 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
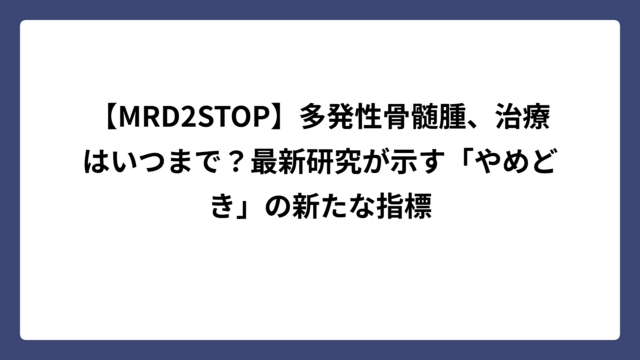 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
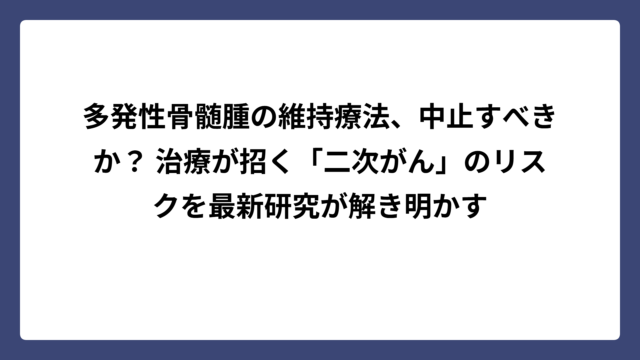 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
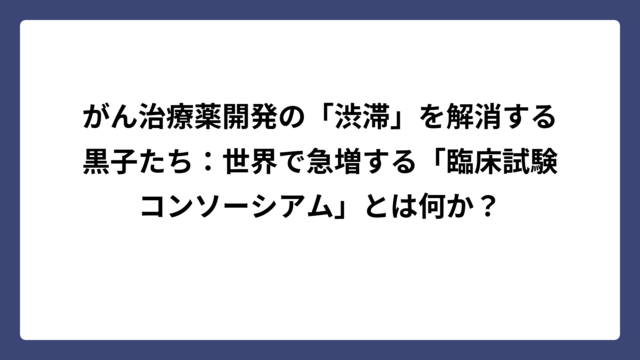 Hematology
Hematology
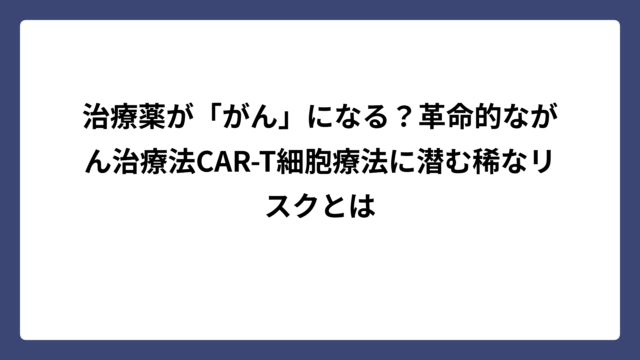 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
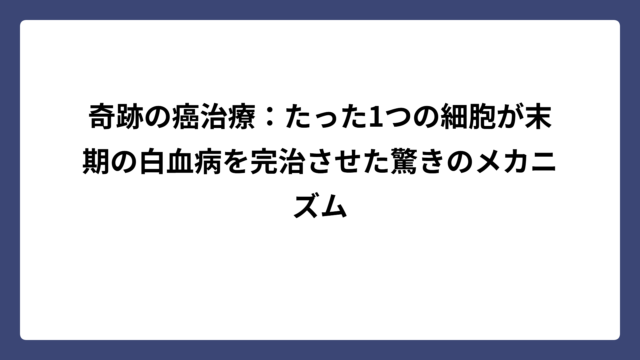 CLL/SLL
CLL/SLL
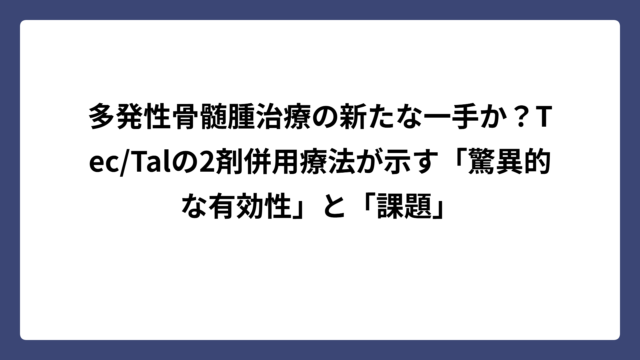 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
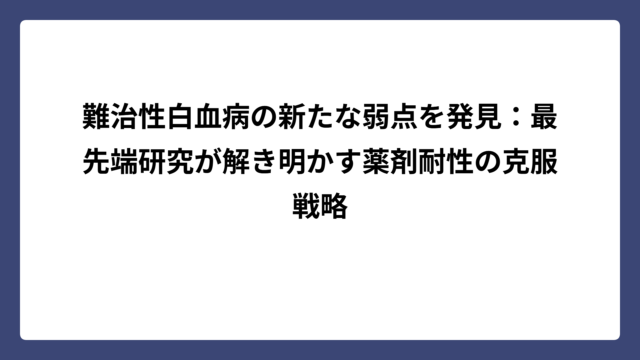 AML/MDS
AML/MDS
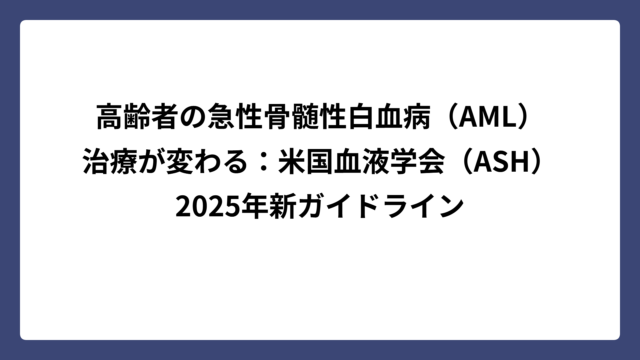 AML/MDS
AML/MDS
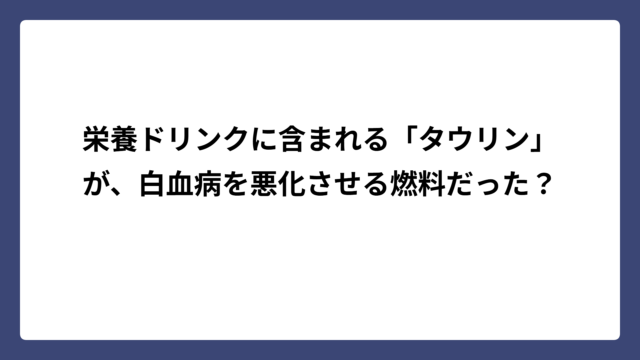 Leukamia
Leukamia
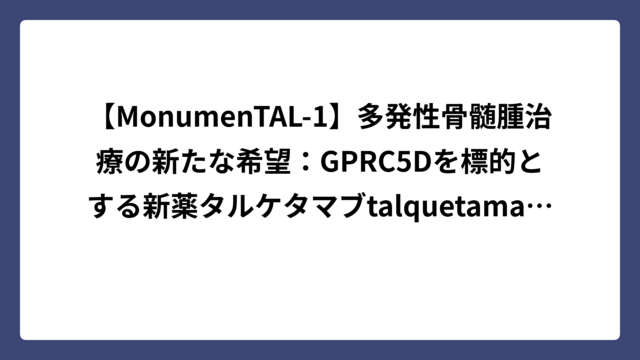 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
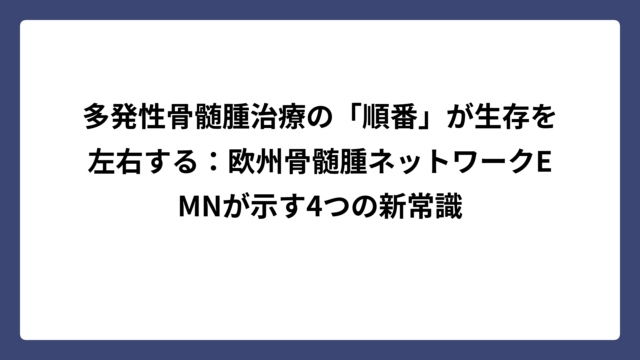 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
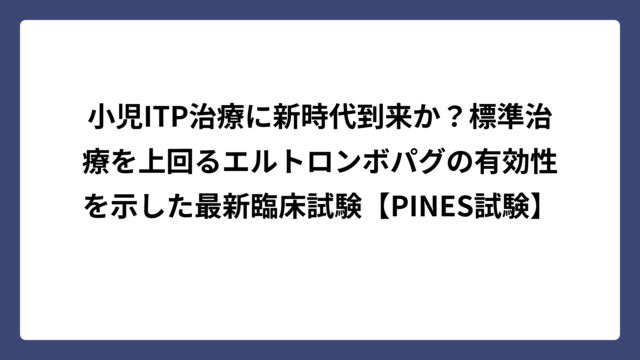 Thrombosis/Hemostasis
Thrombosis/Hemostasis
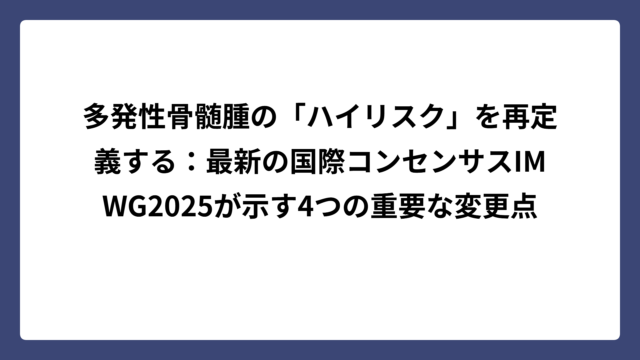 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
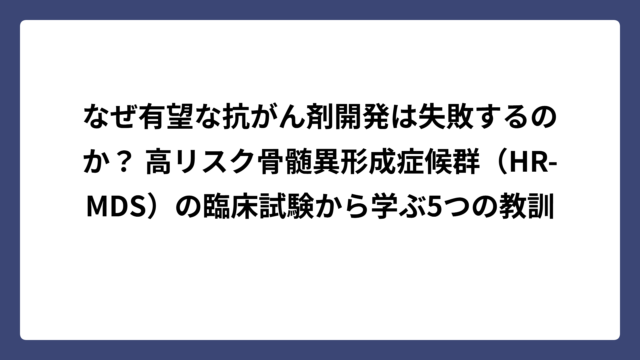 AML/MDS
AML/MDS
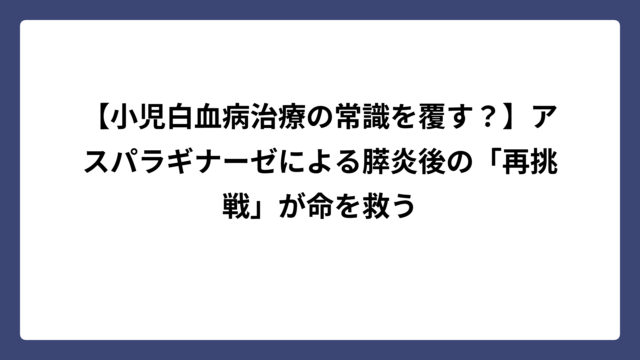 ALL
ALL
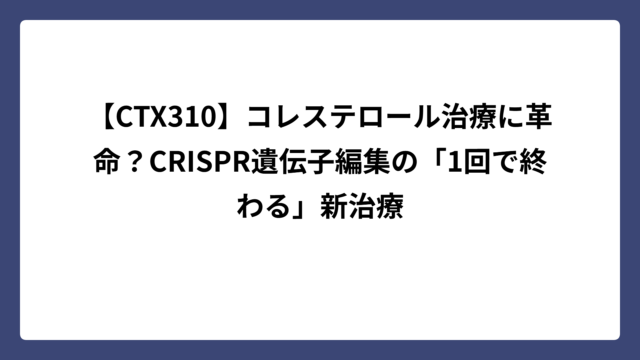 Cardiovascular
Cardiovascular
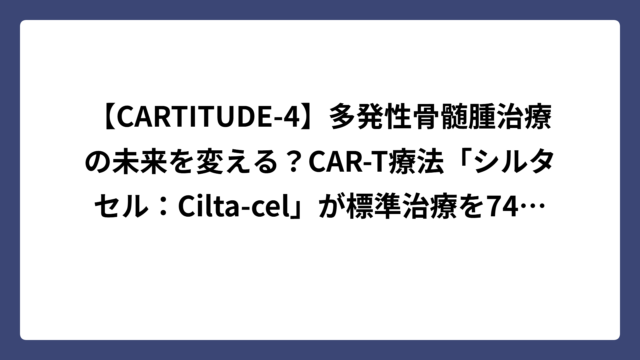 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma
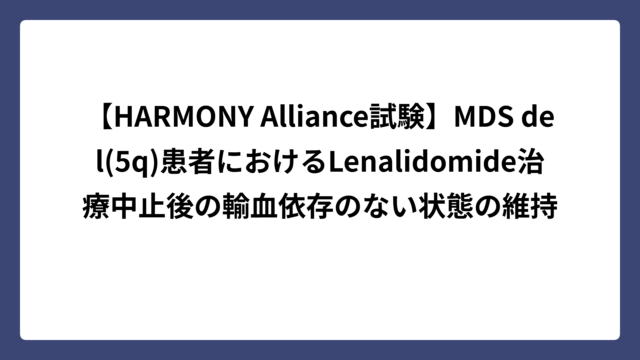 AML/MDS
AML/MDS
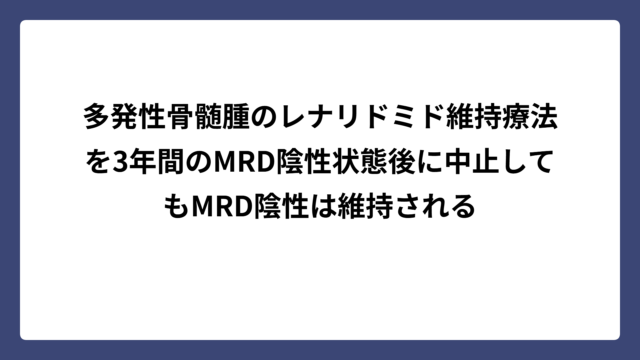 Multiple Myeloma
Multiple Myeloma